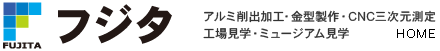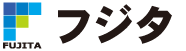皆さん、こんにちは。
これまで鋳造金型の種類と選定方法について書きました。
コラム3回目は「良い金型とは?」について考えてみたいと思います。
良い金型ってどんな金型だと思いますか?
・壊れない
・長く使える
・メンテナンスしやすい
・良い製品ができる
パッと思い浮かぶのはこのくらい…(汗)
型屋としてちょっと恥ずかしいので
この機会にきちんと調べてみようと思います。
まず金型が製品に与える影響を調べてみました。
金型の良しあしは製品のどんなところに影響してくるのでしょうか?
鋳造での成形物は型の形がそのまま出てくるので金型の出来がそのまま
製品に反映されます。
例えば、
金型の寸法精度が悪ければ、後加工の余肉不足や追加工が増え、コストが膨らみます。
金型の製品面が粗ければ、鋳肌が荒れて外観不良になります。
冷却設計やゲート設計が不適切なら、鋳巣・引け巣といった欠陥が発生します。
金型の材質、設計が不適切だと金型の割れが発生します。
※金型って割れるんです!!
このように同じ「アルミ鋳造品」でも、金型の質によって
歩留まり・加工コスト・製品寿命 が大きく変わります。
つまり「金型の質 = 製品の質」 と言っても過言ではないんですねぇ。
そしてもう一つ。
良い金型を作ることはコストアップではなく、
長期目線で見るとむしろコストダウンにつながる点は注目ポイントです。
上述したように、良い金型は後加工の削減や不良率の低減、
金型自体の寿命の長期化を実現します。
それは結果的にトータルコストの削減につながります。
今後脱炭素社会が進んでいくとこの「トータルコストの削減」が
より重要視されると思っています。
それは後加工や不良の削減、低減は
使用するエネルギー削減に直結するからです。
これらを考慮して「良い金型」を定義すると、
・安定した寸法の製品ができる金型、
・表面がきれいな製品ができる金型、
・不良の発生が少ない金型、
・長く、対象のショットを作れる金型、
・環境にやさしい金型
と定義できるかと思います。
それでは良い金型を作るためにどんな知識・技術が必要なのでしょうか?
良い金型を作るために必要な知識と技術
その①:設計技術
金型だけでなく、顧客所有の鋳造機の構造を熟知し、
湯の動きやサイクルタイムを考慮の上
最適な形を設計する技術です。
その②:加工技術
一つの金型はその大きさにより何十、何百もの部品からできています。
もちろん部品の役割によって材質も違えば形状も違う!
快削材~難削材、単純形状~複雑形状と
幅広い材質、形状加工技術が必要となります。
もちろん一つの機械ですべての加工ができるわけではないので
様々な工作機械を使いこなす技術も必要です。
その③:材料・熱処理知識
耐熱性・耐摩耗性が必要な部品は熱処理をして硬度を上げる、
もともと高硬度材を使うなど金型部品の役割にあうよう
適切に材料が選択できる知識も必要です。
その④:現場回線の知恵
実際の鋳造品を観察・解析し、不良や摩耗の原因を金型にフィードバックすることで
今ある金型をよりよくできます。
問題を発見する観察力、
問題を見える化する解析力、
課題を解決できる発想力、解決力が必要です。
いろいろと書きましたが、
実際のところ良い金型は使ってみないとわかりません。
だからこそ当社ではお客様からの声を大切にすることはもちろん、
常に情報を収集し、技術を磨き日々金型づくりに励んでいます。
もし、貴社の製品において
鋳造品のバラつきが大きい
複雑形状の再現が難しい
後加工の手間やコストがかさんでいる
そんなお悩みがあるなら、金型から見直すべきタイミングかもしれません。
さて、いかがでしたか?
製品のコストと品質の話をすると、
「良いものは高い」「安かろう、悪かろう」とよく言われますが、
金型に関しては、金型だけではなく、成形、メンテナンスなど含めた
トータルで見ると必ずしも当てはまらないという事が分かりました。
「コストを抑えてよいもの」が作れる不思議な世界(笑)
それが金型の世界なんですね。
面白い!
気になることがあれば何でも
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
当社は少量多品種生産を得意としており、
部品1点よりお見積りいたします。
その他ピン及び丸い形状の加工事例はこちら
https://www.fujita-k.co.jp/info-cat/lathe/
曲面加工の事例はこちら